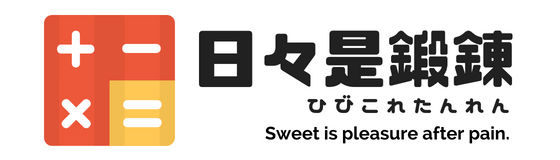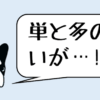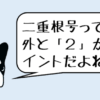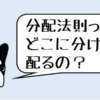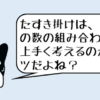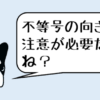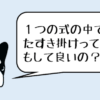数と式|整式について
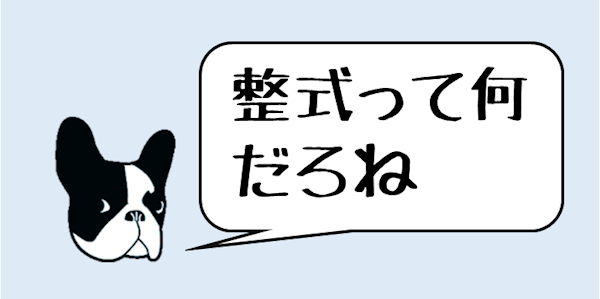
ここでは、整式について学習します。整式は数学1の最初の単元で学習します。
整式はつねに関わる式なので、しっかりと理解しておきましょう。定義をはじめ、分類や扱い方なども合わせて覚えましょう。
整式
整式とは、単項式や多項式で表される式のことです。数学で扱う式全般をまとめて指します。
中学では、文字を含むので文字式と呼んでいたかもしれません。文字式の方が慣れているかもしれませんが、「整式」という用語を積極的に使って慣れましょう。
整式は2種類に分類されます。
整式の分類
- 単項式
- 多項式
単項式
単項式とは、数や文字が積の形で表される式のことです。単項式の一例は以下の通りです。
単項式の一例
\begin{align} \frac{1}{5} a \ , \ 5xy^{2} \end{align}これらは、数や文字が積の形で表されるのが特徴です。ただし、文字を含まない定数も単項式に含まれるので注意しましょう。
単項式かどうかは、乗算の計算記号を省略する前の式に戻せば判断できます。乗算の計算記号を省略する表記ルールは、中学時に学習済みです。
先ほどの例で乗算の計算記号を補うと以下の通りです。
単項式は数や文字が積の形で表される式
\begin{align} &\frac{1}{5} a=\frac{1}{5} \times a \\[ 7pt ] &5xy^{2}=5 \times x \times y \times y \end{align}たとえば、次の式は単項式ではない。
\begin{align} 5xy-3=5 \times x \times y \ \underline{+ \left(-3 \right)} \end{align}理由は、下線部のように和が混じっているから。
このような単項式は、名前の通り、1つ(単)のかたまり(項)として扱われます。ですから、単項式のことを整式の部品と捉えると、多項式のことを理解しやすくなるでしょう。
多項式
多項式とは、複数の単項式の和で表される式のことです。多項式の一例は以下の通りです。
多項式の一例
\begin{align} 2x^{2}-3x+6 \end{align}多項式の見分け方は簡単です。「文字と文字の間に+(プラス)や-(マイナス)の記号があるかどうか」です。一見してすぐに分かります。
多項式の-(マイナス)は減算か?
多項式の定義によれば「複数の単項式の和」となっています。「和」ですから加算(足し算)をイメージします。
しかし、式の中に-(マイナス)の記号が含まれることもあります。こんなとき、どう解釈すれば良いか分からない人もいるかもしれません。これは以下のような解釈をします。
多項式は複数の単項式の和で表される式
\begin{align} &2x^{2}-3x+6 \\[ 7pt ] = \ &2x^{2} \underline{+\left(-3x \right)}+6 \end{align}中学で学習した、正負の数の加減算を思い出しましょう。
正負の数の加減算でのカッコ外し
\begin{align} &-2-\left(-3 \right)-\left(+5 \right)+\left(-6 \right) \\[ 7pt ] = &-2+\left(+3 \right)+\left(-5 \right)+\left(-6 \right) \quad \cdots \text{①} \\[ 7pt ] = &-2+3-5-6 \quad \cdots \text{②} \\[ 7pt ] &\vdots \end{align}正負の数の加減算では、単項式の減算が混じっていたとしても、単項式の加算(①式)に統一してからカッコを外します。ですから、②式であっても、減算が混じった式でなく、加算だけの式と解釈します。
カッコを外す前の①式と、カッコを外した後の②式とをよく見比べてみましょう。
②式では、加算の計算記号やカッコが省略されて、先頭の単項式やカッコ内にあった単項式が順に並んでいます。
多項式は、単項式を順に並べた②式の形をしています。-(マイナス)の記号があったとしても、①式の形から②式の形になった、と解釈しなければなりません。
このことを知らないことが勘違いの原因かもしれません。「加算だけ」という前提で、加算の記号やカッコが省略されていることは、これから整式を扱っていく上で絶対に覚えておくべきことです。
このような前提があるから、交換法則や結合法則を利用することもできます。
多項式の見た目は、単項式をただ並べただけ
なお、正負の数の学習以降では、「-」のことを「引く」と言わずに「マイナス」と言うのが一般的です。
式の「-」を見るたびに減算と捉えてしまうのは、「-」を「引く」と呼ぶ癖が抜けないからかもしれません。プラスやマイナスといった呼び方に早く慣れましょう。
数学1と数学Aは中学数学と高校数学をつなぐ分野
整式の定義に単項式や多項式などの用語が出てきました。これらから分かるように、この単元は中学数学と高校数学をつなぐ単元になります。
この単元だけに限らず、数学1や数学Aは、基本的に中学数学から高校数学への橋渡しになる分野です。いきなり高校数学を学習するには無理があるからです。
ですから、数学1や数学Aでは、中学で扱った題材をより詳しく学習していくのが中心です。そして、数学2や数学Bでは、より高度な内容となる本格的な高校数学を学習します。数学2や数学Bが高校数学の本番です。
数学1の内容が、いくら中学数学の延長であっても、学習していくうちに躓いたり、理解に苦しんだりする箇所が必ず出てきます。そんなときは、中学数学の教科書を開いてみましょう。
躓いたときは、たいてい中学内容の理解が足りていないことが多いものです。中学で学習した内容を確認しながら進めていきましょう。
Recommended books
オススメその1
予習の際に理解が進めば授業のスピードについていくことができ、復習や課題をこなす時間も少なくて済みます。予習や復習の補助教材に向いている教材が『とってもやさしい数学』シリーズです。
とってもやさしい数学1・Aでは2冊とも中学で学習した内容にも触れており、中学内容と高校内容とのつながりを把握しやすい教材です。
一学期のうちは不安を抱えながら学習を進めていく人も多いかと思います。スタートで躓かないためにも易しく取り組みやすい教材を使うのも一つのやり方です。無理をして内容の難しい教材を使うよりもはるかに良いでしょう。
基礎的な内容を扱っているので、数学が苦手な人でも取り組みやすくなっています。興味のある人はぜひ一読してみて下さい。
『高校とってもやさしい数学1・A 改訂版 その1』は「数と式」「2次関数」の単元を扱っています。
『高校とってもやさしい数学1・A 改訂版 その2』は「場合の数」「確率」「整数の性質」「図形の性質」「三角比」の単元を扱っています。
オススメその2
『高校の数学I・Aが1冊でしっかりわかる本』は、これ1冊で数学1・Aの全範囲を復習できます。内容のレベルは「とってもやさしい」シリーズとそれほど変わらず、教科書レベルです。
本書と「とってもやさしい」シリーズのページ数を比較してみました。「とってもやさしい」シリーズは、1冊ごとのページ数が少ないのですが、分冊なのが難点です。
- 高校とってもやさしい数学1・A 改訂版 その1:175ページ
- 高校とってもやさしい数学1・A 改訂版 その2:189ページ
- 高校の数学I・Aが1冊でしっかりわかる本:192ページ
ページ数を比べると分かるように、本書の方が1冊でも遥かにページ数が少ないので、短時間でこなすことができます。
紹介した教材を使うとした場合、高校1年生であれば「とってもやさしい」シリーズで復習し、高校2,3年生であれば『高校の数学I・Aが1冊でしっかりわかる本』と「とってもやさしい」シリーズを組み合わせて復習すると良いでしょう。
こんな人に向いています
- 定期試験や大学受験のための基礎を固めて、成績を上げたい高校生へ。
- 医療看護系入試、高卒認定試験などの対策で、短期間で数学1・Aを理解したい方へ。
- 学び直しや頭の体操をしたい大人の方へ。
さいごにもう一度まとめ
- 整式とは、単項式や多項式で表される式で、単項式や多項式の総称。
- 単項式とは、数や文字が積の形で表される式。
- 多項式とは、複数の単項式の和の形で表される式。
- 多項式は、単項式の和であるが、単項式だけを順に並べた式。
- 整式を扱うときは、つねに和と積を意識しよう。